和柄とは?主な和柄の意味と祈り
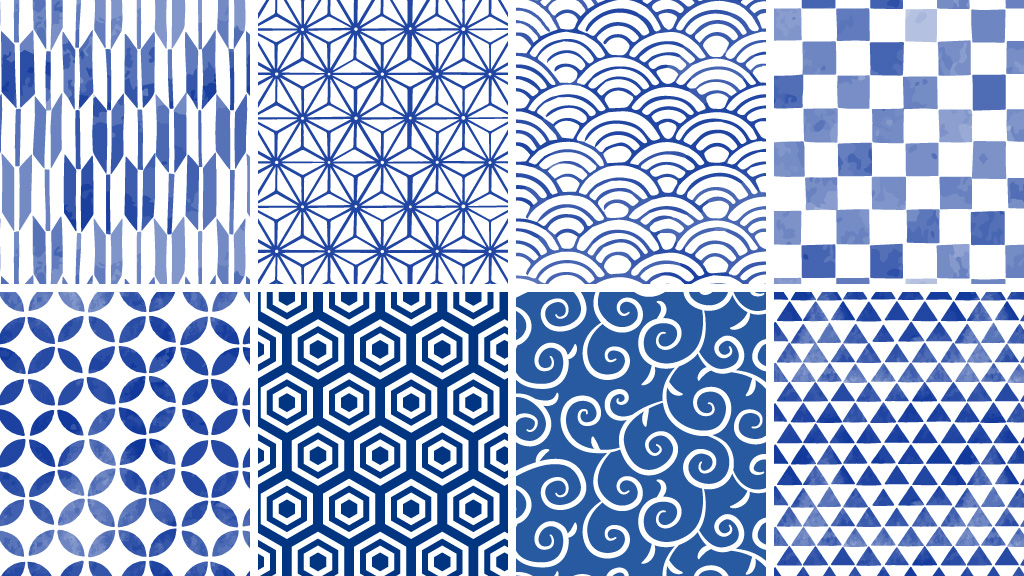
This post is also available in English
和柄とは、日本の伝統文様です。日本で生まれたものだけでなく、海外から渡ってきた柄に日本独自のアレンジを加えたものもあります。最近では、マンガやアニメの影響で、目にしたことがある人が多いのはないでしょうか。
和柄には、それぞれ名前と意味があり、祈りがこめられています。今回は、主な和柄の名前・意味・祈りを紹介しましょう。
コンテンツ
矢絣(やがすり)

矢羽根を繰り返した模様です。大正時代に女学生の間で大流行しました。現在でも大学などの卒業式では「矢絣柄の着物と袴」を身に着けた女性をよく見かけます。矢を射ると、まっすぐ飛び、戻らないことから、「戻らずに幸せになってほしい」という祈りをこめて、嫁入り道具に使われることもありました。
麻の葉(あさのは)
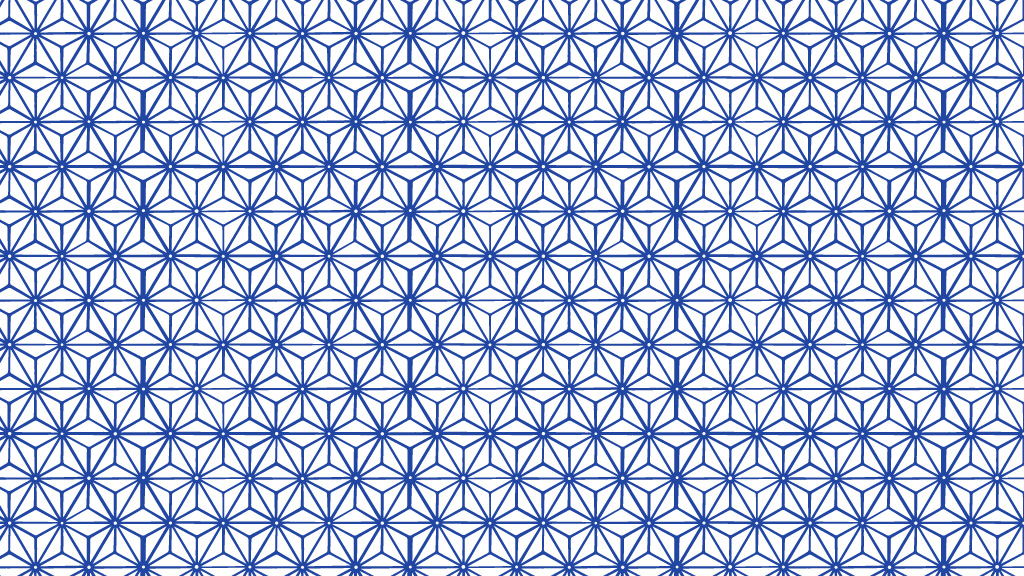
正六角形の頂点を結んだ模様です。麻の葉に似ていることが名前の由来といわれています。麻は、成長が速く、丈夫であることから、「すくすくと育ってほしい」という祈りをこめて、子どもの着物にも使われることがあります。
青海波(せいがいは)
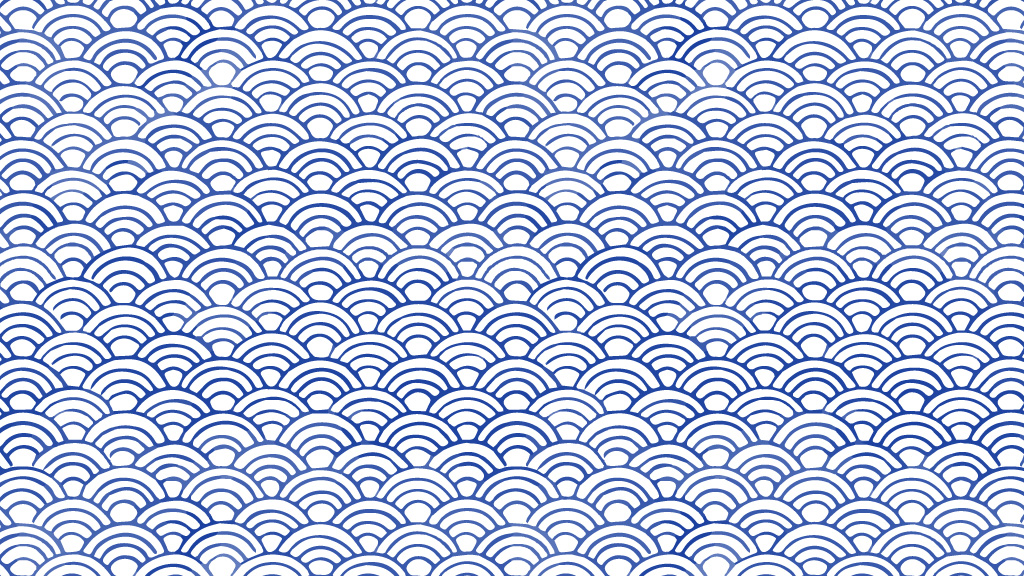
同心円を波のように繰り返した模様です。日本の古い舞曲が、名前の由来となりました。無限に広がる穏やかな波のように見えることから、「未来永劫、平和な暮らしが続きますように」という祈りがこめられています。
市松(いちまつ)
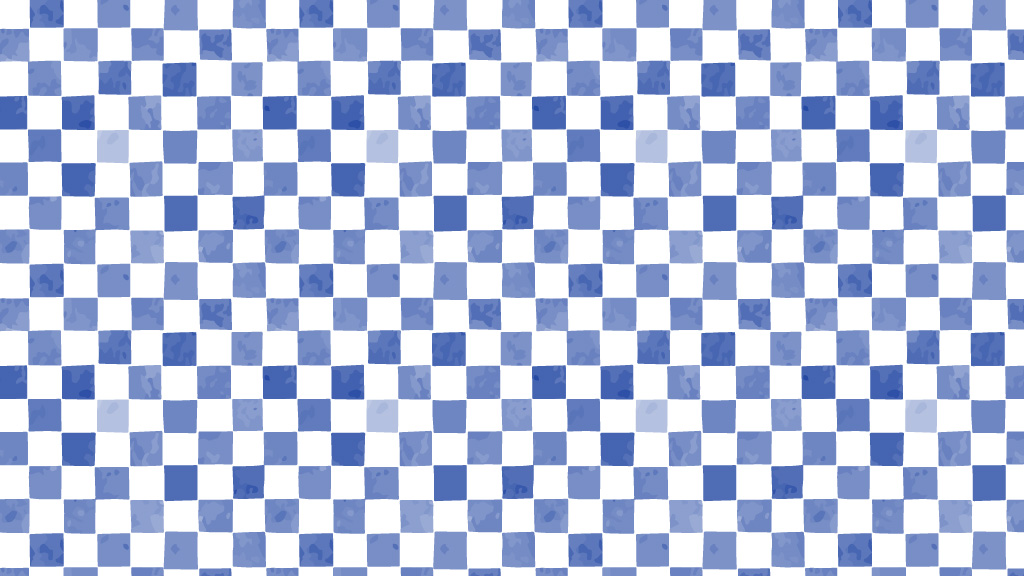
二色の正方形を交互に配置した模様です。石畳(いしだたみ:平たい石を敷きつめた場所)とも呼ばれます。江戸時代の歌舞伎役者が衣装に用いたことが、名前の由来となりました。東京2020オリンピック競技大会のエンブレムのモチーフにも使われています。途切れることなく続くことから、「繁栄しますように」という祈りがこめられています。
七宝(しっぽう)
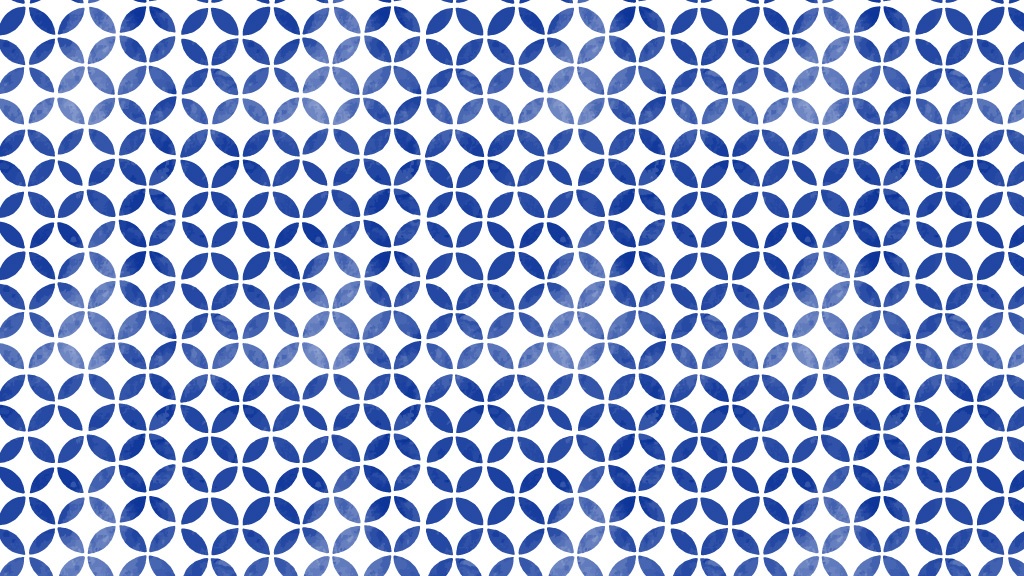
円を、四方に四分の1ずつ、重ねてつないだ模様です。七宝(しっぽう:仏教用語で七種の宝を指す言葉)は四方(しほう:東西南北)から変化しました。永遠に、円(えん)が続くことから、「よいご縁(えん)がありますように」という祈りがこめられています。人の縁は七種の宝に匹敵する価値があると考えられているのです。
亀甲(きっこう)
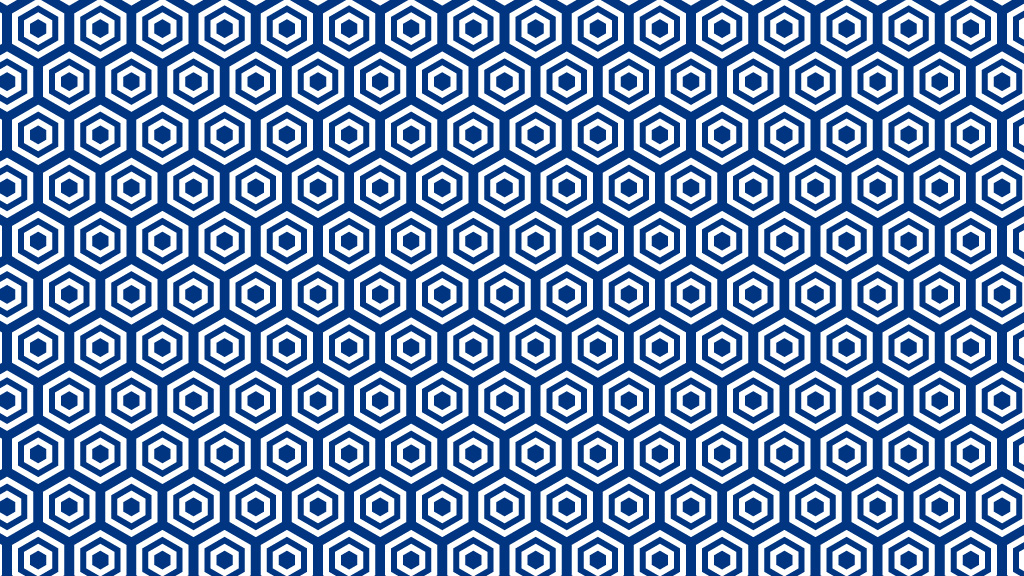
正六角形を繰り返した模様です。亀の甲羅に似ていたことが、名前の由来となりました。「鶴は千年、亀は万年」という言葉があるように、亀が長寿の象徴でもあることから、「長生きできますように」という祈りがこめられています。
唐草(からくさ)
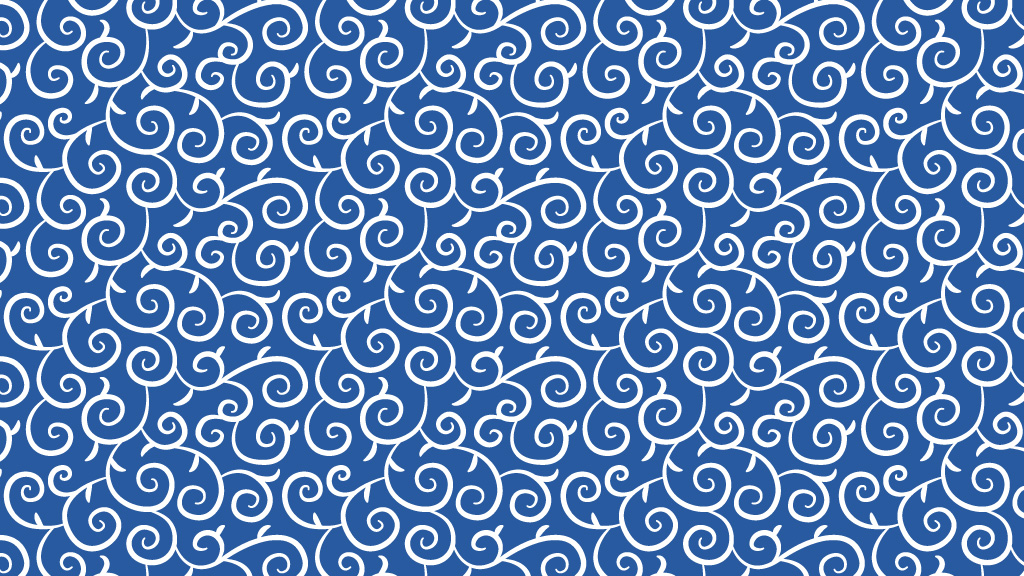
蔓草の蔓や葉が絡み合う模様です。明治から昭和にかけて、唐草模様の風呂敷は人気がありました。どこの家庭にもあったので、今でも泥棒のイラストには、唐草模様の風呂敷を担いだ絵が使われることがあります。どこまでも伸びる蔓は生命力を表すとされることから、「末永く繁栄しますように」という祈りがこめられています。
鱗(うろこ)
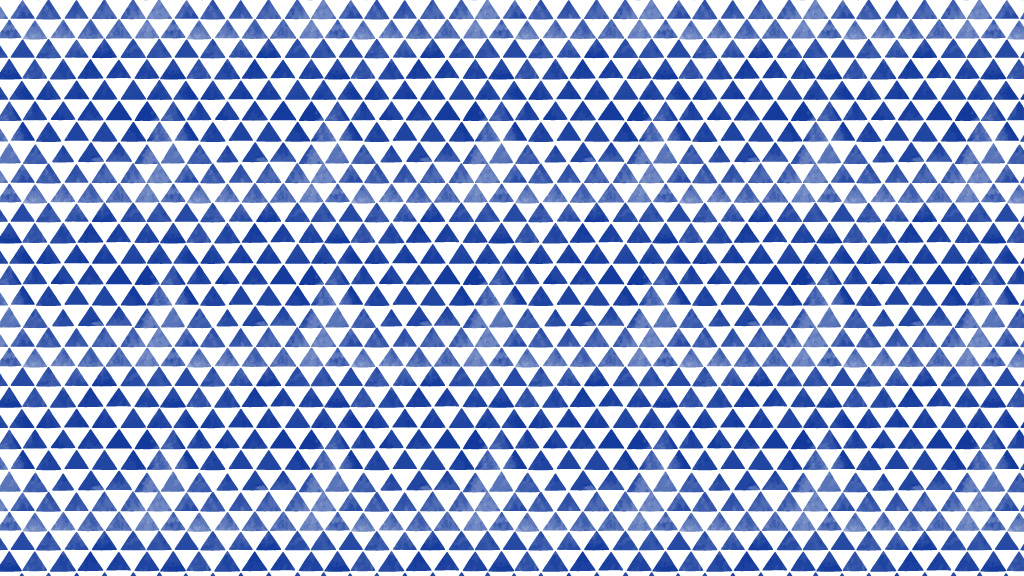
正三角形または二等辺三角形を組み合わせた模様です。魚や蛇の鱗がモチーフと言われます。能(のう)や歌舞伎(かぶき)の衣装にも、よく利用されています。三角形には魔除けの意味があり、鱗は身を守るものでもあることから、「災いや魔性のものが近づきませんように」という祈りがこめられています。
豆絞り
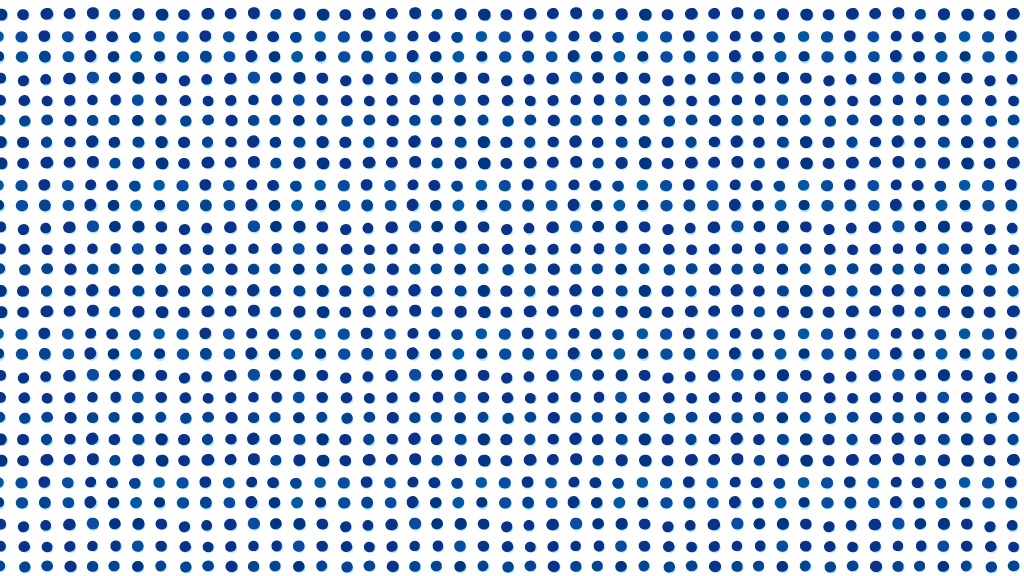
小さい点が等間隔に並べられた模様です。本来は、白地に紺の点、または紺地に白の点を並べた絞り染めの柄を指しました。絞り染めで作られた丸は、色も形もひとつひとつ異なります。現在では、さまざまな色で正円が印刷されたものも指すようになりました。豆は「まめ:からだが丈夫で、精を出して働くこと」と同じ発音で、1粒から多くの豆がとれることから、「商売がうまくいきますように」といった祈りがこめられています。
まとめ
和柄は単なる模様ではなく、それぞれ名前と意味があり、祈りがこめられていることがあります。もし和柄を見かけたら、調べてみると楽しいかもしれません。









